|
| 定価 |
本体53,000円+税 |
| 発行 |
2001年3月 |
| 体裁 |
B5ハードカバー上製205頁 |
| 編集 |
柳田祥三(大阪大学) |
| ISBN |
4−907837−04−6 C3058 |
|
4、色素増感型太陽電池(Gratzel型)の基礎と応用
●近年の技術書では唯一、基礎と理論について詳細に解説
●最近の実用化技術発展の礎となっている応用技術について詳述
出版のねらい
本書は大学、公的研究機関、企業の多くの研究者、技術者が興味と関心を寄せている、いわゆるGratzel(グレッツェル)型太陽電池、その基礎から応用までを、この間、研究開発に関わってきた方々に詳細に内容を執筆していただいたものです。
Gratzel型太陽電池の発表以来高効率をめざして激しい研究開発競争が行われましたが、際立った進展は見られませんでした。それはGratzel型太陽電池は電解質に溶液を用いるため種々の問題を抱えているためと言われています。
ところがこうした問題点を解決する可能性を大いに秘めた研究が、世界にさきがけて、この日本であいついで発表されております。それは、固体電解質型およびゲル電解質型色素増感型太陽電池の研究開発の急速な展開です。
本書は色素増感型太陽電池には多くの企業研究者が興味を持っており、その歴史が長いにもかかわらず、適切な技術書が出版されてないおり、他に先がけていちはやく出版されたものです。基礎研究と理論から最新の応用技術までを一冊に網羅したものとして皆様のお役に立つと確信しております。
●内容目次および執筆者(所属は執筆当時のものです)
第1章 色素増感光電池
大阪大学 名誉教授 坪村 宏,
大阪大学 有機光工学研究センター 松村道雄
1.色素増感(dye sensitization)
2.湿式光電池
3.色素増感光電池
4.色素増感光電流の機構
5.光ガルバニ電池(photo−galvanic cell)
6.色素増感光電池に関する私たちの研究
6−1.基本的問題について
6−2.色素増感光電流を増加させる試みについて
6−3.多孔性ZnO焼結体電極を用いた色素増感型太陽電池の作製
7.高効率色素増感太陽電池の開発のための指針
(1)観測された光起電力について
(2)光電流の見かけの量子収率が22%であったことについて
(3)色素の劣化について
(4)色素増感光電流は電極の欠陥の影響を受けにくいことについて
(5)半導体への色素の吸着特性
8.おわりに
第2章 色素増感と光合成の分子メカニズム
富士写真フィルム(株) 足柄研究所 宮坂 力
1.はじめに
2.光合成初期過程の電子移動
3.光合成のしくみから学ぶこと
4.半導体の色素増感の分子メカニズム
5.増感光電流の分極依存性
6.効率のさまざまな表しかた
7.エネルギー移動の制御
8.色素のエネルギーレベルにかかわる制御
9.増感色素の励起頻度のこと
10.おわりに
第3章 石原産業における色素増感酸化チタン太陽電池開発の経緯と成果
テラメックス(株) 特機部 松本雅光,
(株)シグナスエンタープライズ 村澤貞夫
1.はじめに
2.酸化チタンカラーコピー
3.酸化チタン多孔質電極
4.電極の表面処理
5.電池特性
6.電池の内部抵抗
7.多重散乱の効果
8.酸化チタン膜内部における電子の拡散長
9.固体化の試み
10.あとがき
第4章 色素増感型太陽電池(Gratzel電池)の基礎
名古屋工業技術研究所 垰田博史
1.はじめに
2.太陽電池の現状と問題点
3.湿式太陽電池と色素増感の特徴
4.色素増感型太陽電池(Gratzel電池)の構造と特徴
4−1.半導体電極
4−2.電解液
4−3.対極
4−4.ルテニウム錯体
4−5.酸化チタン多孔質膜
4−6.Gratzel色素の特徴
5.色素増感型太陽電池(Gratzel電池)の性能
6.色素増感型太陽電池(Gratzel電池)のコスト
7.色素増感型太陽電池(Gratzel電池)の課題
8.おわりに
第5章 Gratzel電池の色素増感ダイナミクス
大阪大学 大学院工学研究科 北村隆之,
柳田祥三
1.はじめに
2.変換効率を決定する因子
3.ルテニウムポリピリジン錯体から多孔質TiO2薄膜への超高速電子移動
3−1.フェルミの黄金律
3−2.酸化チタンへの電子注入
3−3.注入電子の色素への逆電子移動
3−4.ヨウ素イオンから色素への電子注入速度の観測
3−5.注入電子の電解質への逆電子移動過程
4.無機半導体微結晶への色素吸着
5.メソスコピックTiO2薄膜の電子移動特性
5−1.TiO2の物性
5−2.電子移動のモデル
5−3.時間分解測定による解析
5−4.周波数応答による解析
6.おわりに
第6章 色素増感太陽電池の研究開発動向と技術課題
物質工学工業技術研究所 荒川裕則
1.はじめに
2.グレッツェル・セルの作成と性能の再現性確認
(1)均一で多孔質なチタニア薄膜の調製
(2)光散乱中心の添加
(3)チタニア薄膜のTiCl4処理
(4)Ru色素固定チタニア薄膜の塩基処理
(5)色素増感太陽電池の性能
3.新しい色素増感太陽電池の開発動向
3−1.チタニア以外の酸化物半導体薄膜光電極を用いる色素増感太陽電池
3−2.新規な高性能金属錯体色素の開発
3−3.有機色素を用いた色素増感太陽電池の研究開発
4.グレッツェル・セルの耐久性,安定性について
(1)セルの耐久性
(2)セルのスケールアップ
(3)グレッツェル・セルの擬固体化と固体化
5.今後の技術課題
第7章 色素増感型太陽電池用光電極材料の新規作製手法
岐阜大学 大学院工学研究科 吉田 司,
箕浦秀樹
1.序論
1−1.半導体薄膜作製法と色素増感型太陽電池特性向上の歴史
1−2.コロイド塗布・焼成法の問題点と半導体薄膜新規作製法の必要性
1−3.色素増感型太陽電池光アノード材料作製の新規アプローチ−酸化亜鉛/色素ハイブリッド薄膜の電気化学的自己組織的形成
2.酸化亜鉛/色素ハイブリッド薄膜の電気化学的自己組織化
2−1.薄膜作製原理と手法
2−2.酸化亜鉛/色素3次元複合体構造の解明と自己組織化モデル
3.酸化亜鉛/色素ハイブリッド薄膜の光電気化学特性
4.結論−色素増感型太陽電池開発における電気化学的自己組織化法の将来展望
第8章 有機物質を使用した固体型色素増感太陽電池
大阪大学 大学院工学研究科 伊藤省吾,
柳田祥三
1.はじめに
1−1.固体化の必要性
1−2.固体型色素増感太陽電池の分類
2.イオン伝導性固体型色素増感太陽電池
2−1.イオン伝導性ポリマーゲル
3.イオン伝導性低分子ゲル
4.電子伝導性有機物質を使用した固体型色素増感太陽電池
4−1.有機導電性高分子
5.有機低分子ホール輸送材
6.もう一つの太陽電池(有機p-n接合を用いた固体系太陽電池)
7.おわりに
第9章 p-型半導体を用いる色素増感型太陽電池の固体化
静岡大学 工学部 昆野昭則
1. 緒言
2. 固体型色素増感太陽電池
2−1.湿式色素増感型太陽電池における電解質層の役割と問題点
(1)電解質層の役割
(2)電解質層の問題点
2−2. 電解質層の固体化
(1)電解液をゲル状固体化する方法
(2)有機ホール輸送層を用いる方法
(3)p-型半導体を用いる方法
3. 銅塩p-型半導体
3−1. p-型半導体電極を用いる湿式色素増感型太陽電池
3−2. 銅塩p-型半導体を用いる固体型色素増感太陽電池
(1)概要としくみ
(2)TiO2電極およびp-型半導体層の作成法
(3)電池の評価と性能
(4)特長および問題点と対策
4. 今後の展望
第10章 擬固体色素増感太陽電池の開発と新用途開拓−東芝の取り組み−
(株)東芝 研究開発センター 早瀬修二,櫻井正敏,御子柴智,角野裕康,米澤 実,内藤勝之
1.はじめに
2.擬固体色素増感太陽電池の開発−ゲル電解質−
2−1.電解質を固体化する意味
2−2.擬固体化色素増感太陽電池の作製プロセスと,必要とされる電解液の特性
2−3.ゲル電解液前駆体を設計するための問題点
2−4.ゲル電解質の特性
2−5.太陽電池特性
2−6.結論
3.色素増感セルの多色多層パターン化による新規応用
3−1.色素増感セルの可能性
3−2.色素増感型セルの特徴
3−3.波長選択+透光性→カラーセンサ
3−4.波長選択+パターン化→看板/カラーフィルタ太陽電池
3−5.パターン化+透光性→複数構造物位置決めセンサ
3−6.まとめ
第11章 Gratzel電池−世界の開発研究の動向と今後の展望
大阪大学 大学院工学研究科 柳田祥三
1.はじめに
2.INAPにおける開発研究
3.ECNにおける研究状況
4.STAにおける研究状況
5.Solaronixにおける研究状況
6.今後の展望
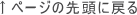 |
|